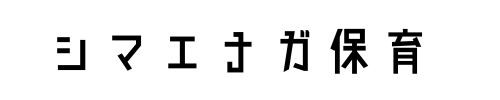はじめに:「どうやって読めばいいの?」と悩むパパママへ
「絵本の読み聞かせが大事って聞くけど、どうやって読めばいいの?」「そもそも、ちゃんと聞いてくれない…」そんなふうに思ったことはありませんか?
私自身、保育現場でたくさんの絵本を読んできましたが、中にはじっと聞いていられない子もいました。しかし、読み聞かせのポイントを押さえながら繰り返し続けていくうちに、「これ読んで!」と嬉しそうに絵本を持ってくる子が増えてたり、同じフレーズを一緒に口ずさむようになったり・・・。
読み聞かせを通じて、言葉を覚えたり、気持ちを表現するようになったりする姿を見て、改めて「絵本の時間ってすごく大切なんだな」と感じました。
この記事では、「読み聞かせってどうやるの?」「何を意識すればいいの?」と悩んでいるパパママのために、楽しく絵本の時間を過ごすコツを5つのポイントにまとめました。
読み聞かせのメリットとは?
読み聞かせには、大きく分けて5つの効果があるとされています。それは、言葉の力や想像力を育むだけでなく、子どもの心を豊かにし、親子の絆を深める素敵な時間になります。ぜひ、「親子で楽しむ時間」として、絵本を取り入れたいものですね!
①言葉を覚える力が育つ(言語能力の向上)
②脳が発達し考える力が育つ(認知能力の向上)
③集中力の向上
④感情を学ぶ(共感力・自己表現力)
⑤親子の絆が深まる
詳しくはこちらの記事で解説しているので時間があればぜひ読んでみてくださいね♪
効果的な絵本の読み聞かせ5つのポイント!
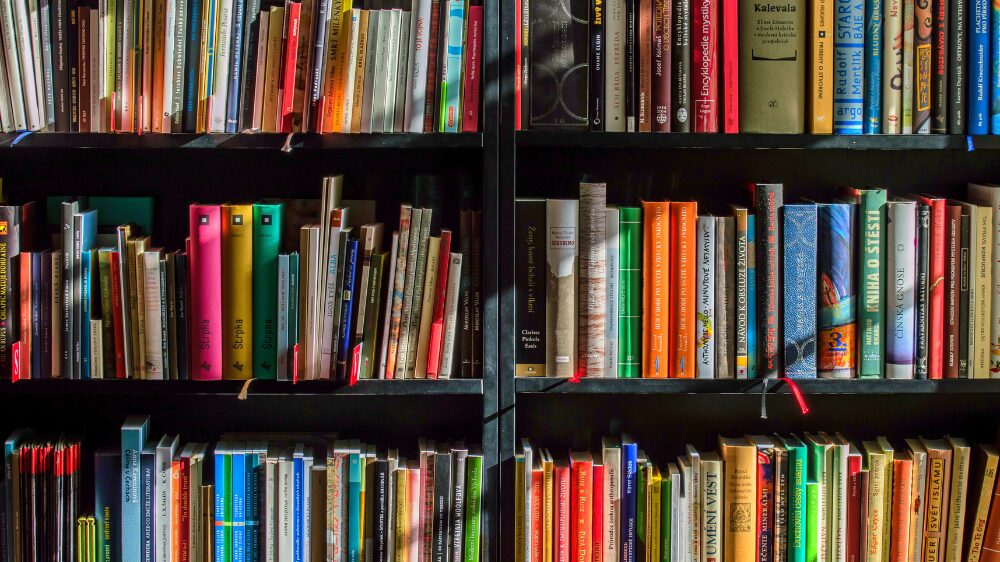
①子どもの年齢に合った絵本を選ぶ
「どんな絵本を選べばいいの?」と悩んだことはありませんか?実は、子どもの成長段階に合わせた絵本を選ぶことで、より楽しめる読み聞かせをすることができます。
0歳:見る・触る・聞くが楽しい絵本
この時期の赤ちゃんは、視力がまだ発達途中であるため、はっきりした色使いやシンプルなデザインの絵本に反応しやすいです。まだ言葉を理解する段階ではないため、 視覚・触覚・聴覚を刺激する絵本 (布絵本やしかけ絵本など触って楽しめるタイプの絵本)を選ぶことがおすすめです。
1歳:リズムや繰り返しのある絵本
1歳ごろになると、言葉を少しずつ理解し、指差しや簡単な発語が始まります。 まだ長い文章は理解しにくいので、 繰り返しのフレーズや、リズムのある言葉 がでてくる絵本がピッタリ。
「ぴょーん!」や「もこもこもこ」などのシンプルで音が楽しい絵本は、子どもが喜びやすいです。
2歳:簡単なストーリー性のある絵本
2歳を過ぎると、少しずつ物語の流れを理解できるようになります。短いお話や、身近な生活の出来事(お風呂・ごはん・おでかけなど)がテーマになった絵本を選ぶと、子どもも「これ知ってる!」共感しやすくなります。
3歳:簡単なストーリーと繰り返しのあるお話
3歳児は 少し長めのお話を聞くことができるようになり、「どうなるの?」と物語の展開を楽しむ力がついてきます。 また、登場人物に感情移入することも増えてきます。
4歳:感情の理解を深めるお話がぴったり!
4歳になると、 自分の感情をコントロールする力(自己制御力)が少しずつ育ちます。 そのため、登場人物の気持ちに共感しながら、「どうしてかな?」と考えられるようになります。
5歳:少し長めの物語にチャレンジ!
5歳になると、 より長いお話を楽しめるようになり、登場人物の成長や変化に興味を持つようになります。 また、ユーモアのあるお話や冒険の要素がある物語にも夢中になります。
6歳:考える力を育むお話がぴったり!
6歳になると、小学校入学を控え、 より複雑な物語や、道徳的なテーマのあるお話を理解できるようになります。 「どうしてこうなったの?」「もし自分だったら?」と考える力を育てる絵本がピッタリです。
②楽しく読むための環境を整える

「せっかく読み聞かせを始めたのに、なんだか落ち着いてくれない…」「すぐにページをめくったり、どこかに行ってしまう…」 そんな経験はありませんか?実は、ちょっとした工夫で絵本を楽しむ環境を整えることができます。
1. 読み聞かせに適した時間帯を見つける
おすすめの時間帯
・寝る前・お昼寝前のリラックスタイム
・ お風呂上がりで体が落ち着いているとき
・ 食事の後のまったりした時間
子どもが落ち着いている時間を選ぶと、絵本の世界に入り込みやすくなります。
2. 静かで落ち着ける場所を作る
環境を整えるコツ
・ テレビやスマホはオフに!(映像や音があると気が散りやすい)
・周りにおもちゃを置かない(遊びたくなってしまうので、視界に入らないようにする)
・明るすぎず、暗すぎないちょうどいい照明を(寝る前は少し暗めの方が◎)
テレビやスマホの音が気になる場所だと、子どもの集中力が続きません。読み聞かせのときは、できるだけ静かな環境を作ることが大切です。
3. 読み聞かせの姿勢を工夫する
おすすめの姿勢
・子どもを膝の上に座らせる(密着すると安心感UP!)
・ 横に並んで、絵本を一緒に見る
・ 布団の中やソファでくつろぎながら読むのも◎
子どもを膝の上に座らせたり、横に並んで読むことで、安心感が生まれます。一緒にページをめくるのも楽しい時間になりますよ。
③感情をこめて読むと効果がUP!
「絵本を読んでいても、つい棒読みになってしまう…」
そんなふうに感じたことはありませんか?実は、感情をこめた読み聞かせは、子どもの理解力や興味をグッと引き出す力があります。
1. 声のトーンやスピードを工夫する
- 怖いシーンは 声をひそめてゆっくりと…
- ワクワクする場面では 明るく弾むような声で!
- 登場人物によって 声色を変えて演じてみるのも◎
登場人物によって声色を変えたり、大事なシーンではゆっくり読んだりすると、子どもが物語に入り込みやすくなりますよ。
2. 絵本のリズムを大げさに読む
- 『ぴょーん!』(まつおか たつひで)
- 『どんどこ ももんちゃん』(とよた かずひこ)
- 『もこもこもこ』(谷川俊太郎)
オノマトペが多く出てくる絵本で、リズムにのって読むのがおすすめです。
言葉そのものの響きや、くり返しの楽しさを感じることができるので、内容を理解する前の子でも、身体でリズムを感じて楽しむことができます。
大人が楽しみながら読むことで、子どももまねして言うこともあります。
④子どもとの対話を大切にする

絵本を「読む」だけではもったいない!読みながら子どもとやりとりをすることで、語彙力や会話力を育てることができます。
1. 「これ何かな?」と質問する
絵本に出てくる動物・食べ物・物などを指差しながら声をかけてみましょう。
「これ、何色かな?」「どんな顔してる?」などの質問をすると、子どもが自分で考え、表現する力が育ちます。
2. 「この後どうなるかな?」と想像させる
少し慣れてきたら、ストーリーの途中で「このあとどうなると思う?」と声をかけてみてください。
正解を求める必要はありません。自由な発想でOK!もし答えに詰まっても、「そう思ったんだね!」と共感することで、子どもは安心して発言できるようになります。
子どもが考える→自分の言葉で伝える、という体験は、思考力や読解力の土台にもなります。
3. 絵本の内容を日常に結びつける
絵本を読み終わったあとも、日常会話に絵本の話題を取り入れてみると、記憶に残りやすくなります。
「今日、お外でねこさん見たね」「この食べ物、おうちにもあるね!」と、絵本の世界と現実をリンクさせると、子どもがより身近に感じるようになります。
☘️ 無理に話させようとしなくても大丈夫!
最初は反応がなくても、少しずつ「まねっこ」や「指差し」から始まり、
やがて自分の言葉で反応してくれるようになります。
「楽しそうに読む」、そして「興味を示したときに拾ってあげる」それだけでも十分ですよ♪
⑤無理なく続けることが一番大切
「じっと聞いてくれない…」「毎日続けるのは大変」そんなときは、無理なく続けられる方法を試してみましょう。
1. 短い時間でもOK!
最初から長く読もうとせず、1~2分でも大丈夫。日常のすき間にちょっと読むだけでも、「絵本=楽しい時間」になっていきます。子どもが興味を持つところから始めましょう。
2. 子どもが好きな本を何度も読む
「またこの本!?」って思ったこと、ありませんか?(あるあるですよね…!)でも、子どもにとっての“繰り返し”は成長の宝庫なんです。
- 同じ表現を何度も聞く → 語彙や言い回しを覚える
- ストーリー展開を知ってる → 安心感や先を読む力が育つ
- 「次はこれがくる!」という喜び → 達成感・理解の実感
子どもの好きな本を繰り返し読んであげるといいですね!
3. 「聞いてくれない」ことを気にしすぎない
途中で遊び始めても、絵本を開いているだけでOK。絵本を開いて、親が楽しそうに読んでいる姿を見せるだけで、子どもは“心に残る体験”をしているものです。無理に聞かせようとせず、楽しい時間を作ることが大切ですね。
まとめ:“読み聞かせ”は、親子の大切なコミュニケーション

初めての読み聞かせ、うまくできるか不安になることもあるかもしれません。
でも大丈夫。完璧じゃなくていいんです。
絵本を開いて、子どもと一緒に笑ったり驚いたり、そんなささやかな時間の中に、
子どもの「言葉」や「心」がゆっくりと育っていきます。
今日ご紹介した5つのポイントは、
特別な準備がいらず、親子で気軽に楽しめるものばかりです。
あなたの声、あなたの表情、そのすべてが、子どもにとっては大好きな“物語の世界”の入り口なんです。
ぜひ、あなたらしいペースで、無理なく、楽しく、絵本との時間を続けてみてくださいね。